新生児に育児用ミルクを与える際の注意点
新生児とは、生後4週間(28日)未満の赤ちゃんです。母乳は、赤ちゃんの成長に必要な栄養がすべて含まれています。育児用ミルクは、母乳の代用品として、牛乳を原料に母乳に似せて作られている食品です。
年々、品質が向上している育児用ミルクは、母乳に不足しがちな鉄分などが強化されているなどのメリットがあります。「思うように母乳がでない」「赤ちゃんの体重が増えない」など母乳育児が難しい場合の心強いアイテムです。新生児に与える際には、注意点があるので、確認しておきましょう。
調乳する際は、70度以上のお湯を使う
育児用ミルク(調整粉乳)は無菌ではないため、体の機能が未熟な乳幼児に与える際には殺菌が必要です。殺菌が不十分な場合、腸炎や髄膜炎など重大な感染症を引き起こす可能性があります。
感染症による死亡症例は、感染した乳幼児の2~5割にのぼり、死亡に至らない場合であっても、神経障害などの合併症が継続するケースもあるのです。この感染症は、大人であっても感染する可能性はありますが、症状はかなり軽症で済むとされています。一方で、生後28日未満の新生児では、高リスクで感染し重症化してしまうので、十分な殺菌が重要です。
感染症の原因菌は、70度以上で感染力が失われます。社団法人日本乳業協会では、80度前後の熱湯を使うか、調乳後の育児用ミルクをいったん80度前後に加熱してから冷ます調乳方法を推奨しています。
やけどに注意!
熱湯で調乳後、そのまま与えるとやけどをしてしまいます。必ず人肌程度に冷ましてから、赤ちゃんに与えましょう。
ミネラルウォーターは使わない
ミネラルウォーターは、ミネラルが多く含まれているため、赤ちゃんの腎臓には負担が大きいです。また、消化不良を起こす可能性があるので、避けましょう。
調乳後2時間経ってしまった育児用ミルクは捨てる
感染症のリスクを少なくするには、菌の繁殖を抑える注意が大切です。調乳後は、長時間放置せず、2時間以内に飲み切らなかった育児用ミルクは廃棄しましょう。
新生児にミルクを飲ませるべき?見極めのサイン
新生児は、授乳量が足りていない場合や飲みすぎている場合に、サインを出します。赤ちゃんの様子をよく観察して、心配なサインがある場合は、専門医に相談しましょう。
授乳量が足りている場合のサイン
● 顔の血色がよい
● 肌の張りがよい
● 機嫌がよい
● おしっこが1日6回以上でている
● 体重が増えている(1日平均30g増加が目安。それ以上でも心配はいりません。)
飲み過ぎている場合のサイン
● 便秘・下痢がみられる
● 乳汁をよく吐くが、体重は減っていない
● おなかが張って、苦しそうに泣く
● 口からよく乳汁をこぼす
● 授乳間隔が4時間~5時間空いてしまう場合が多い
授乳量が足りていない場合のサイン
● 元気がない
● 体重が増えない
● 激しい嘔吐があり、体重が減る
● おしっこが1日6回もでていない
● 授乳後、すぐにミルクを欲しがる
授乳量が足りていない場合は、育児用ミルクで補う必要があるかもしれません。専門医に相談してみましょう。
生後の成長、月齢にあわせたミルクの量の目安

赤ちゃんが生まれてから離乳食が始まるまでは、すべての栄養を母乳や育児用ミルクで補っています。赤ちゃんの成長にともなって少しずつ与える授乳量を増やしていきましょう。離乳食が始まったら、授乳量は増やさず、食事からの栄養量の割合を徐々に増やしていきます。
生後0~7日
生後1週間頃までの新生児は、授乳の目安量が毎日増えます。下記に示すのはあくまで目安量なので、医療機関のスタッフに相談しながら進めていきましょう。
● 1回あたりの授乳量の目安 生後0日目は10ml(1日毎に10mlずつ増加)
● 1日あたりの授乳回数の目安 8回
生後1~2週間
育児用ミルクに記載されている規定量を目安にしましょう。多少の増減は気にしなくてもOKです。ただし、多すぎると吐き戻す場合があるので注意が必要です。
● 1回あたりの授乳量の目安 80ml
● 1日あたりの授乳回数の目安 7~8回
生後3~4週間
赤ちゃんの体重に合わせて、育児用ミルクに記載の規定量を確認して与えましょう。
● 1回あたりの授乳量の目安 100ml~120ml
● 1日あたりの授乳回数の目安 6~8回
生後1~2カ月
● 1回あたりの授乳量の目安 120ml~160ml
● 1日あたりの授乳回数の目安 6回
生後2~3カ月
● 1回あたりの授乳量の目安 120ml~160ml
● 1日あたりの授乳回数の目安 6回
生後3~5カ月
● 1回あたりの授乳量の目安 200ml
● 1日あたりの授乳回数の目安 5回
生後5~7カ月
● 1回あたりの授乳量の目安 200ml
● 1日あたりの授乳回数の目安 5回
※1日1回の離乳食がスタート
生後7~9カ月
● 1回あたりの授乳量の目安 200ml
● 1日あたりの授乳回数の目安 5回
※離乳食が1日2回になる
生後9~12カ月
● 1回あたりの授乳量の目安 200ml
● 1日あたりの授乳回数の目安 5回
※離乳食が1日3回になる
新生児期の混合栄養にするときのミルク量
混合栄養の場合は、「母乳のあとに30~40ml程度が目安」となります。ミルクを与えすぎてしまうと、母乳の分泌量が減ってしまうので注意しましょう。また、母乳の場合は、赤ちゃんが欲しがる分だけ与えます。ただし、体重が過度に増えていたり、吐き戻してしまう場合は多すぎるかもしれません。
母乳とミルクのバランスのとりかた
新生児に母乳とミルクを混合で与える場合は、胸の張り具合や生活スタイルに合わせて、母乳と育児用ミルクのバランスをとっていきましょう。つぎのような混合栄養の進め方があります。
まずは母乳を、つぎにミルクを
初めに母乳を飲ませて、飲み足りない分を育児用ミルクで補うようにします。新生児の頃は、ミルクは欲しがる分だけ与えましょう。
交互に母乳とミルクをあげる
“おっぱいが張っているときは母乳を、張っていないときは育児用ミルクを”といったように、母乳が出ないタイミングで育児用ミルクを補うとよいでしょう。例えば、3時間おきに授乳をさせる場合、「朝6時に母乳、9時に育児用ミルク、12時に母乳」といった形で、母乳と育児用ミルクを交互にするとやりやすいです。
午後にミルクをプラスする
母乳は朝が出やすく、夜になっていくにつれて少なくなる傾向があります。そのため、午前中は母乳だけにして、午後から母乳に加えて育児用ミルクも併用するとよいでしょう。
日中だけミルクにする
仕事などで授乳が難しい場合は、日中は保育園などに預けて育児用ミルクを与え、朝・夕は母乳を与えます。
心強い「育児用ミルク」の助けを借りて、健全な赤ちゃんの成長を
新生児期は、赤ちゃんもママのおっぱいも授乳に慣れていません。そのため、思うように飲んでくれなかったり、赤ちゃんの体重が増えなかったりと問題を抱えやすい時期です。育児用ミルクは、そんなときの心強いサポーターになります。
赤ちゃんとのスキンシップを心がけ、発するサインに目を向けましょう。授乳量が不足しているようであれば育児用ミルクを活用していきます。新生児は抵抗力が弱いので、衛生面や使用する水などに気をつけながらの調乳・授乳が肝心です。目安量を参考にしながら、あなたに合ったスタイルで授乳してあげましょう。





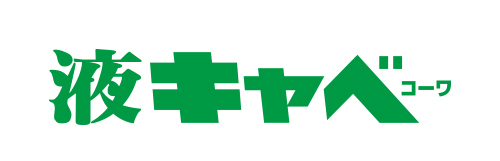















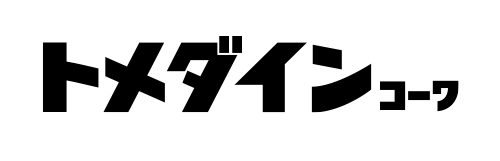



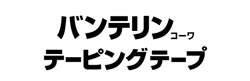







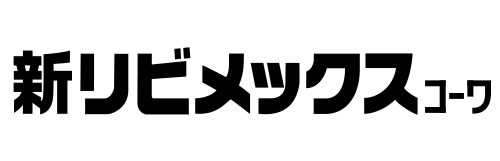






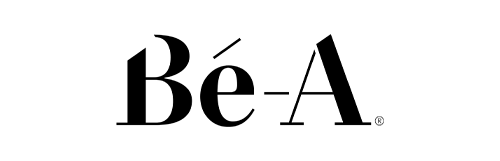




































各ブランドの商品一覧をご確認いただけます。